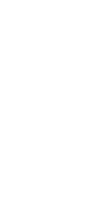各地域の高麗人蔘
五千年も前から中国、朝鮮半島、日本などで、薬効の高い生薬のひとつとして珍重されてきた高麗人蔘。 日本で栽培が始まったのは江戸時代、八代将軍吉宗のとき。栽培は困難を極めましたが、それを成功させ、今なお受け継がれているのが、会津(福島県)、信州(長野県)、そして雲州(島根県)です。 由志園では、毎年秋に収穫する自社農園の「雲州人蔘」だけでなく、信州産、会津産の人蔘も園内の人蔘方(※)で「紅蔘」に加工しています。 人蔘は風土や栽培法によって、姿や風味などが異なります。日本三大産地の人蔘を摂り比べて、風味の違いなどもお楽しみください。


[ 生人蔘 ]

[ 紅蔘 ]

【栽培地など】
-
会津産
田んぼを畑にした粘土質の土で育ち、薬効が高まり始めた四年根をトラクターで掘り起こし、収穫します。
-
信州産
標高800メートルの高原の、柔らかく水はけの良い土で育ち、下に向かってグングン根を伸ばします。六年根を収穫。
-
雲州産
ホクホクした黒ぼく土で、江戸時代から伝わる栽培法で育てられます。六年根を専用の道具を使って1本1本、手で掘り起こします。
【姿と風味】
-
会津産
胴と足から尾が伸び、雲州産と信州産の間のような姿です。四年根で大きさはやや小ぶりで、苦味や香りは少なめです。
-
信州産
雲州産や会津産に比べ、大ぶりの主根から足と尾がまっすぐ長く伸び、水分が多めです。特に生は、清涼感のあるすっきりした苦味です。
-
雲州産
胴(主根)から足(支根)が元気に広がり、足には尾(細根、ひげ根)がたくさん。大地の栄養をしっかり吸収し、香ばしさや深み、コクのあるバランスのとれた苦味です。
※風味の感じ方は個人差があります。
紅蔘とは
生人蔘を蒸して水分15%以下に乾燥させたもの。
紅蔘にすることで風味や成分が凝縮され、
保存もよくなります。
-

蒸籠に生人蔘を並べ3時間蒸す。 -

粗熱がとれたら干しザルに並べ、乾燥室へ。 -

約50度の乾燥室で、10日から2週間程度、 乾燥させると紅蔘ができる。